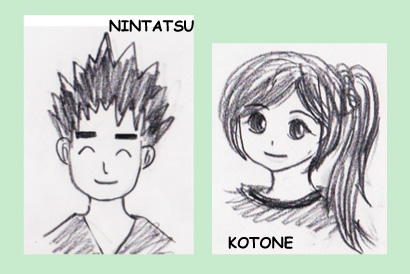ハイパーフレッシュナブルこてぃすと ~優しさの調和~ (1)
1年で最も過ごしやすいといわれる季節になった。
そのわりに今日は朝からやけにじめじめと湿っぽい。 梅雨入りにはまだまだ遠いはずなのに、時折生温い風が頬を撫で、気分まで憂鬱になりそうだった。
私の名前は凛堂琴音(りんどうことね) 年齢は30歳と約半年。
自分の中にもう一つ別の魂が存在することを除けば、ごくごく普通のどこにでもいる平凡なパート主婦である。
別の魂というのは人間ではなく、天上界の神の「使い」と魔界の「魔物」 の間に生まれたハーフである。名を龍月(りゅうげつ)という。
彼女の両親はとある事情により2世界では育てることができず、体が形成される前に魂を地上界、すなわち人間が住むこの世界に落とした。
そして、たまたま私の魂の型と適合したため滞在することになった。
約半年前、生まれて30年目にして初めて龍月と会うことができた。
そのきっかけとなったのが私の誕生日だった。
彼女の婚約者を名乗る日向(ぴゅう)という使いの男性が天上界から訪ねて来たことだった。
「夢逢石(むおうせき)」という石を使えば夢の中で龍月と話ができるというもので、半信半疑の私はこの石を使わせてもらい、何度か彼女と話をすることができた。
けれどもこの石は実は魔力で精製されたもので、継続使用すると使用者の命を奪ってしまう恐れがあったため全て破壊された。
それ以後は龍月と会うことも頭の中で声が聞こえてくるということなどもなかった。
私は2ヶ月ほど前に、住み慣れた京の都から美濃の地に引っ越してきた。
念願のマイホームを建てたのである。
ここは全国でも有数の柿の生産地のため至る場所に柿畑がある。
柿の木は知っているとはいえ、せいぜい他所の家の庭やお寺の境内で見かける程度であった私には、畑一面に低木の柿の木が広がっているというのは新鮮な光景だった。
木には青々とした若葉が繁り、白黄色の小さな花が爽やかに映るが、夜になると枝の別れ具合が長い両腕を広げて獲物を待ち構えている怪物のシルエットに見えてしまい、日が落ちてからはあまり近づきたくない場所だった。
それなのになぜ日没後に外出しているかというと、夕食準備中に牛乳が殆ど残っていないことに気づいたからである。片付けを済ませた後、最寄のスーパーまで買いに行っていたのだった。
ようやく歩き慣れた畑道。雨は既に止んでいる。
私は外灯の近くでふと足を止めた。
静寂の中、かすかに陰鬱な気配を感じた。
(雨のせいかな…)
気に止めず歩き出そうとすると
「おい」
いきなり後ろから声をかけられた。
「えっ?」
びくっとした私が振り返った先には鋭い目をした男性が立っていた。
黒髪に黒っぽい瞳、歳は20代後半くらい。
初夏だというのに黒のモッズ風コートを着ていた。
そのコートというのも少し変わっていて、フロントが短めの斜め比翼仕立てになっており、端が白と深い黄色の色で縁どられ、袖周りもまた同じラインのデザインだった。
身長の割には華奢な体つきで、見目は良いけれどもネガティブな草食系男子といった印象を受けた。
「うん?ええっと…ああっ!」
私は見覚えある姿に魂消げた。
「龍…?ほし…星太郎!」
「龍星(りゅうせい)だ」
彼は眉間に皺を寄せた。 本名はわかっていた。
だがあまりにも唐突すぎたのと、私の中でやたら「星」の印象が強かったためか全然違う名前が口をついて出た。
「あ、うん、そうやった。ってなんでこんなとこにいるん?もしや不意打ちか!?」
私は安さに負けてつい購入してしまった特売の大根をエコバッグから取り出し身構えた。
龍星は生粋の魔物で、龍月の父違いの兄である。
初めて彼に会ったのは5年近く前のこと。
「お前の弾く箏(こと)の音色が原因でオカンが病気になったんだよ!どうしてくれるんだよ!」と要約すればこんな感じで、一方的な敵対心を持たれ命まで狙われるという事件があった。
日本の弦楽器の一つ「箏」、桐でできた本体に13本の絃が張られた楽器だ。
学生時代私は箏曲部に所属しており、卒業後も月に何度か顧問の先生の所へお稽古に通い続けている。
5年前、傷心の日々を送っていた私は箏を心の拠り所にしていた。
けれども、その箏を奏でる音が魔界では不協和音となり騒音被害を出していたらしい。
信じられないかもしれないが、この世界は人間たちが暮らす地上界の他に、天上界と魔界の2つの世界とも繋がっているらしい。
天上界には神様と彼らを手助けする「使い」と呼ばれる者が住み、天上界の者達は、神様の意向を人間に伝える役割と同時に人間を正しい方向へ導く活動を行っている。
一方魔界では、魔王を中心とした「フレリ」という組織で構成されており、彼ら魔物は人間の憎しみ、悲しみ、怒りなど負の感情につけ入り悪の道へ誘おうとしている。
なぜ魔界に被害が及んだかというと、龍月の魂が天上界から地上界へ落とされる際、彼女の父から、地上界でも幸せに暮らせるようにと「絶対的な祈り」を込められたためだった。
その祈りによって私の悲しみの感情と箏の音色が共鳴し合い、魔界では騒音被害が広がってしまうという事態が発生したのだった。
心の支えでもあった箏をやめるわけにもいかず、私は「こてぃすと」の技を習得することに決める。
「こてぃすと」とは箏演奏者であり、かつ箏術(ことじゅつ)を使う者のことを指す。
箏術とは演奏者の気持ちによって、聴く人の心の有り方を変化させる一種の術で、箏を演奏する際に使う爪を持っていれば使用できる。
引っ掻くように払うと風を起こしたり、複数の絃鳴らすと衝撃波を発生させたり、防壁を作れたり等、バラエティに富んだ技を繰り出すことができる。
基本の箏術を習得した私は彼に腹蹴りをくらうという暴力を振るわれたりもしたが、最終的には彼の母が現れ無事であることと、箏の音色は心の持ちようで様変わりし、騒音にならないという事実が判明した。
これでめでたしめでたしと思いきや、魔物およびフレリ達は、地上界で暮らしている使いの魂が入った人間を探し出し、片っぱしから天上界に強制送還または排除するのが目的なので、事情を知らぬ魔物達が私もその使いの一人とみなして襲撃してくるかもしれないということで、引き続きこてぃすととしての活動を余儀なくされた。
このような経緯で彼には良い思い出が全くなかった。
それゆえ久しぶりの再会といえど躊躇と驚き以外の念は沸き起こってこなかった。
そもそも魔物というものは直接人間に関与することはないらしく、このように人前に姿を現すということは禍いをもたらしにきたのではないかと自然と警戒心を抱かざるを得なかった。
そんな私の心を見透かしたのか龍星はため息をついた。
「別件で近辺を通りかかっただけで特に用はない」
「じゃあ声かけんでもええやん」
「……」
呼び止めといて用はないってどないやねん!と呆れたが、彼はまだ含むところがあるような複雑な表情をしていた。
「こてぃすとは辞めたのか?」
その瞬間私はギクリとした。5年前の去り際の自分の台詞を思い起こした。
「こてぃすとの特訓をして魔物なんか追い払ってみんなを守る」とか正義のヒーローばりの意気込みを宣言していた気がする。
若気の至りだったと振り返り近況を伝えた。
「辞めてはないよ。もしもに備えて、技をすぐ出せるようにはしてるけど、近づく魔物もいなくなったし、今は悠々自適な箏ライフを楽しんでるよ」
箏爪(ことづめ)を持参していないというのに私は「すぐに出せる」などと大嘘をついてしまった。
「そっちはどうなん?お母さんは元気?」
会ったついでなので気軽な感じで尋ねた。
「変わりなく過ごしているようだ」
「一緒に暮らしてるんかと思った。龍月もお母さんから話聞いてたって言ってたから」
「近い所にはいる」
「一人暮らしってこと?」
彼は頷いた。思いのほか会話が弾まず、私が質問攻めしているようだった。
「そういえば、一緒にいたお付の女の人は?」
「紗佐(ささ)か?あいつは俺の部下で普段は別の職務についている」
「フレリやったっけ。そんな組織体制やったんや」
すると彼は突然バツが悪そうに視線を逸らした。
「龍月から色々と聞いている。その…あの時は悪かったな、早とちりして」
「え、いや、もう昔のことやし…」
私は狼狽した。あの凶悪と言っても過言ではない龍月の兄が数年ぶりの再会にしてまず謝罪の言葉。
敵意むき出しの当時の彼とは打って変わってしおらしくなったというか、とげとげしさがなくなった気がする。
いや、実は物静かな性格で、執着している事柄に触れると豹変するタイプだったのかもしれない。
「ところで、お前は魔力を持つことに抵抗はないか?」
「魔力?持ったことないから何とも。 家事が捗るなら使いたいもんやけど…何で?」
「自分の魔力の保管先を探している」
「魔力を保管?自分で持ってるのが全てじゃないの?」
「日常使う力とは別に、緩河(ゆるかわ)にいくらか蓄えておけるようになっている」
「ゆるかわ?」
「天上界では星空(ほしぞら)と呼んでいるものだ」
「星空って、確か魂が彷徨ってる空間やったっけ…」
私はまだそう遠くない過去の記憶を手繰り寄せた。
半年前、龍月と会った時に彼女の魂が「星空」といういわば天上界と魔界を行き来できる「みち」に存在することを知った。
「呼び方違うんや。魔物も利用してるん?」
「緩河は何層にも重なってできている空間だ。浮遊魂はその最上面…最上面に見える位置に存在する。対して、魔力保管(ストック)スペースはその下に設けられている。
従来魔物には、基本的に備わっている魔力と保管用の魔力の二種類ある。魔力が強いフレリ達は原則として緩河ストックを利用しなければならない」
「盗まれたりするから?」
「奪取対策も兼ねているが、特定のフレリのみ強大な力を得ないよう調整するためだ」
「ふうん。それなら星空…緩河に保管しとけばええやん。うちフツーの人間やで」
その途端彼の表情がやや曇った。
「フツーの人よりは魔界や天上界と関わってしもた人間かな。でも、生活には何も影響出てないよ」
「そういう奴が適しているんだ。お前達のコードの隙間なら安全だろうと」
「隙間収納にぴったり!みたいな言い方やな」
コードというのは人の魂から出ている線状のようなもので、私と龍月はその型が一致するらしい。 通常2つの魂の間にはわずかに隙間が空いている。
そんな狭い所に自分の魔力を保管したいなんて全く理由がわからない。
「龍月はお前の判断に任せると言っていた」
「ホントに?なんかマズイこと考えてない?」
「いや、そんなことは…」
「嘘や。だいたい天上界や魔界から誰か来る時は厄介事持ち込みって決まってるんや。龍月のお父さんやってそうやったし」
「天上界の奴らと一緒にするな。上手くいけば移動作業は数分で終わるはずだ」
「そのはっきり言い切れてないのが怖いんやけど。他にも魂持ってる人いるやろ」
「お前暇だろう」
「人を暇人にせんといてよ。こう見えて仕事してるんやからな」
私はデリカシーのない彼にイラっとした。
「そういうわけで申し訳ないけど、お役に立つことができません…じゃっ!」
私はくるりと前を向くと数10メートル先の自宅に向かって足早に進み出した。
(全く人の魂をなんやと思って…でも、魔法使ってみたかったかもなあ…って、あかんあかん!魔物の誘惑にのるなんて!)
私は両頬をパチパチたたいて気を引き締めた。
ふと前方に目をやると、自転車にまたがった上下ウコン色の寝間着姿のおじいさんが近づいて来ていた。かなりフラフラ運転だ。
しかもその後ろからは乗用車が距離を縮めていた。
おじいさんは一旦立ち止まり後ろを振り返ると車に気づき、再びハンドルを握り直すと加速した。
が、フラフラ運転は変わらず、むしろさっきよりも蛇行運転がひどくなり、車も追い越しできない状況だった。そんなことおじいさんはつゆ気にも留めていない。
私は道路脇側溝まで寄った。寄りすぎれば雨で湿った草花に足を滑らせ、運が悪ければ顔面から畑へダイブして泥まみれになってしまうのは明確である。
おじいさんが道路脇に寄ったためか、背後にぴったりくっついていた車が少しスピードを上げて追い越そうとした。
またもやおじいさんは車の前にふらーり、そして今度は私の方にゆらーり…
(え?避けやな…!って)
「あっ!」
左足がずるっと滑り、バランスを崩して手をバタバタさせていると、腕をがしっと掴まれた。
「星太郎!ありが…うわっ!落ちる!」
体を支えてくれるかと思いきや、龍星も一緒になって畑に落ちかけたその時、ゴン!と彼の頭に額をぶつけた。
ズキッと痛みが走った。
「いたたたた…」
どたっと尻餅をついた私はどうにか体を起こした。
幸いなことに乾いた土の上だったので泥まみれになることはなかった。
私は砂を軽く払うと向かいに倒れ込んだ龍星に違和感を覚えた。
「あれ?」
起き上がった彼の姿はどう見ても子供だった。
175センチはあったであろう身長が約30センチは縮んでおり、私よりも小さくなっていた。
人間でいうなら小学校5、6年生くらいだろうか。それだけではない。頭には左右に広がった柿の木の枝のような鹿の形に似た角が2本生えていた。
「ツノ?星太郎って鹿の魔物やったん!?」
「違う…だいたい魔界に鹿はいない」
彼は静かに怒っていたが「星太郎」呼びについては特に触れなかった。
大人の姿と比べて、どこかしら幼さが残っている顔つきに少しだけ警戒心が解れた。
「角なんてあったんやな」
「普段は隠している。人間に似せたほうが警戒されづらいからな」
彼はそう言って目を伏せた。
「へえ~てっきり、いろんなとこにぶつけたり引っ掛けたりするからやと思った」
「そのバカな発想はどこから来る?」
「バカな発想じゃないよ、斬新と言って」
呆れている彼に私は胸を張って言い返した。
「こういうのって、もう1回同じ現象起こすと戻ったりするんちゃう?」
「こら、やめろ!」
私は有無言わせず、彼の額めがけて頭突きをかました。
ゴツーン!
「痛い!」
結果、痛かっただけで彼の姿は小さいままだった。
「痛ってぇなバカ…」
「ごめんごめん」
額をさする彼に私は軽く謝った。
「たまに大きな衝撃を受けると縮むことがある。大抵数日すれば治る」
じゃあ、大事には至らないのかとほっと安心しようとしかけた時、彼の表情が強ばった。
「まずい」
私が何がと問いかけようとする前に
「手を出せ」
「手?え、あ、はい」
彼は私の腕をぐいと掴むと手の平を上に向けて思い切り叩いた。
バチーン!
「痛ったい!何する…え、水!?」
それはまるでミニ噴水とでも名付けられるかのように、勢いよく水を噴き上げていた。
「どっから出てきたんこれ?」
あたふたする私に彼は意気消沈した様子で言った。
「どうやらさっきの衝撃で魔力がお前に移ってしまったらしい」
「もしかして謀ったん?」
「お前達のコードには飛んでいない。別の場所だ」
「手放したかったなら結果オーライじゃ…」
「それがストックまるごと飛んだようだ。だから魔界へ帰る力も残っていない」
「帰れへん…?前の時は魔窟(まくつ)とかいうとこから接触してたやん」
魔窟とは魔物が棲む魔の巣窟のことで、自在に空間を作ることができると、以前龍月の父から説明を受けたはずと曖昧な記憶をたどった。
「魔窟は魔界の特別空間であって、直接地上界と接触しているわけじゃない」
「え、じゃあ、今日はどうやってここへ?」
「ワープだ」
「ワープ?そんな魔法のようなことが…ああ、魔物やから魔法使えるか」
私はなんだか頭が痛くなってきた。
「と、とりあえず家へ戻ろう。詳しい話聞くから…」
彼は拒絶することなく静かに頷いた。
自宅に到着して玄関ドアを開けると、パタパタパタと駆けてくるスリッパ音とともに夫の仁達(にんたつ)がにこやかに出迎えてくれた。
「おかえり~…その子は?」
私の後ろにいるフードを目深にかぶった少年に仁達は目をぱちくりさせていた。
「星太郎」
「違う…その変な呼び方やめろ」
龍星は横目で私を睨んだ。
大人に比べて気迫も半減され、怖くなくなっていた私はぷぷっと笑った。
「本名は龍星」
「龍星って、龍月のお兄さんの?どう見ても子供のような…あ、僕は琴音ちゃんの夫で凛堂仁達(りんどうにんたつ)と言います」
初対面でもすぐにその違和感には気づいたらしい。
それにしてもさすが記憶力抜群の仁達。
3年以上も前に話した登場人物をよく思い出せたものだ。
「そうそうその人。偶然そこで会うて、ゴツーンて頭ぶつけたら小っこくなってしもてさー。おまけに魔力もほぼスッカラカンになって…いや、移動やっけ?よくわからんのやけど…」
「ふーん、そうなんか…とにかく、座ってゆっくり話そう」
リビングへ案内しようとする仁達に龍星は躊躇いの表情を見せた。
「上がるのか…?」
「他に選択肢が?」
「…わかった」
「あっ、土足厳禁なんで」
彼は渋々承知すると靴を脱いで玄関に上がり、さっとフードをとった。
仁達はぎょっとしていた。
「わあ、すごいもの付けてるんやね…」
「元から付いてるもんやで」
「…そうなんや。てっきり何かのイベントで仮装でもしてたのかと思ったよ。ははは」
温厚篤実な彼の時たま出る天然さに私も驚きを隠せないことがあった。
龍星は特にコメントせず黙って見つめていたが、玄関正面の階段を見上げると厳しい顔つきになった。
その視線の先には1匹の斑模様の動物が毛を逆立てていた。
つぶらな瞳と丸い耳、ふさふさの長い尻尾が特徴の小さな虎である。彼は箏の精霊ワラビ。
ワラビは私の以前使っていた箏の精霊である。普段は滅多に姿を見せない気難しい性格の彼が、今はグウゥと唸り声を出して龍星を睨みつけていた。
お互い一歩も動かなかったが、数秒経つとワラビは階段を駆け下り、大きく口を開けて龍星に飛びかかった。
龍星は腕で払いのけたが、ワラビはもう一度頭めがけてジャンプしようとした。
「ワラビ!やめっ!」
私は彼らの間に入ったが、頬に軽く猫パンチを食らった。
「痛っ!何をそんなに荒立ててるん?昔のことはいいやろ」
「魔物が地上界に現れることは凶事でしかない」
彼もまた5年前の事件当時、被害にあった1匹である。精霊は、魔物が容易に地上界の人間に近づけないように守る役割も担っている。
ワラビは低い声で答えたが私は首を横に振った。
「今は魔力カラッポやって。何もできへん、人間以下なんやで」
「それは語弊があると思うよ…」
仁達の呟きツッコミに龍星は同調していると思われるような不服そうな眼差しだった。
一触即発ムードの中、階段の手すりの上を滑り落ちてきた小動物がいた。ゼンマイである。
ゼンマイは私の2つ目の箏の精霊で、ネズミとキツネザルを足して二で割ったような体型、身長25センチほどの生き物である。目が異常にくりっとしているため、笑うと特に珍妙な面になる。性格は好奇心旺盛でマイペースだった。
ゼンマイは龍星の膝にぴょんと飛び乗ると、トトトトと上に向かって走っていき、肩までたどり着くと頬をすりすりとこすりつけた。
「何のつもりだ?」
彼はゼンマイをひょいとつまみ上げた。ゼンマイは嬉しそうに目を細め、手足をぶんぶん振っていた。
「ふぬぬぬーん!ふぬぬぬっ!」
「何て言ってるん?」
私はこの中で唯一ゼンマイの言葉が解せるワラビに通訳を求めた。
「よろしく鹿の精霊さん…と」
ワラビは棒読みで訳した。
「鹿…?ぷっ、ナイスボケ!ゼンマイ!」
「ふぬーん!」
私とゼンマイはハイタッチするように指を合わせた。
「あ、ワラビもう行くん?」
ワラビは自室…箏の置いてある2階へ戻ろうとしていた。彼は立ち止まりちらりと振り返ると
「害がなさそうなら用はない」
言い残し階段を上がっていってしまった。
ゼンマイの振る舞いを見て「安全な魔物」だと確信したのだろうか。
ゼンマイといえば、今度は龍星の頭に乗っかって角を指でつついてみたり、ふさふさの尻尾でぽんぽんと跳ねてみたり、遠足の自由行動の園児のように無邪気に遊んでいた。
「鬱陶しい」
彼は手で払いのけると、ゼンマイはポーンと飛ばされた。床に激突するかと思いきや、くるくるくるっと回転し見事に両足で着地した。
「ふぬぬ~ん!」
フットワークの軽さに感動した私と仁達。
「すごい!」
拍手を送った。
「ゼンマイのおかげで助かったよ、ありがとう」
私はしゃがんでゼンマイの頭を撫でた。彼は喜ぶと再び龍星の脚に飛び乗った。
そして今度はお腹あたりに飛びつくと、よじよじとそのまま一直線に上り、肩まで来るとちょこんと座った。
「ふぬーんぬん」
ゼンマイは龍星を見上げて楽しそうに鳴いていた。
「ぷっ…めっちゃ懐かれてる…同類やと思われてるやん。よかったな」
私は爆笑寸前になったのを必死にこらえていた。
冷酷なイメージだった彼が子供の姿になった途端、魔物以前に精霊と間違えられるというなんとも微笑ましい光景に愉快な気分だった。
「邪魔だ」
不愉快そうな龍星はゼンマイを摘み軽く放り投げた。ゼンマイは
「ぬふーん」
と飛び上がりその勢いのまま階段を駆けていった。
一段落後、私達はダイニングに入った。
ダイニングリビングが一体化したLDKスペースは、全体的に明るい温かみのある茶色でまとめられ、アクセントとして引戸や間仕切り、ダイニングテーブル椅子には格子デザインを取り入れた和モダンテイストに仕上げてもらっていた。
のどが渇いていた私はキッチンへ向かった。
お茶を飲もうとシンク横のカウンタースペースに置いていた耐熱ガラスポットのフタを取った。
「星太郎もお茶飲む?」
冷蔵庫を開けて茶葉を選んでいた私は龍星に尋ねると、彼は神妙な顔をした。
「おちゃ?」
「魔界にはないんか。お茶は大多数の日本人が飲んでる飲み物やな。一般的に緑茶のことを指してて、緑茶にも、煎茶、かぶせ茶、玄米茶、ほうじ茶とかいろんな種類があるよ。
種類の大きな違いは葉っぱを日光にあてる時間の違いかな。玉露とかかぶせ茶は日照時間が少ないから、苦味が少なくまろやかな口当たりになる…」
「待て。そんな長い説明は求めていない」
お茶の種類の説明を遮った彼に仁達は
「琴音ちゃんはお茶通なんやよ」
と微笑んだ。
「通まではいかんなあ。色んなの飲んでるうちに覚えただけ。寝る時間前やし、カフェインの少ないほうじ茶でいい?」
「ああ、うん」
龍星は何でもいいやというふうな返事をした。
私が保温ポットの湯を注いでいると
「リリフか」
彼はキッチンカウンター脇に置いてあった白いチャック付き袋を手に取った。
袋には 「リリフ4193~天からの恵み~」という文字の下に、双葉を象ったファンシーなキャラクターのイラストが描かれていた。
「リリフ4193(よいくさ)」は天上界で育てられたリリフという薬草を原料にした爽快味のサプリメントである。龍月の父が仕える神様がリリフを育てており、天上界では主に解毒、浄化剤として使われていた。
それが人間にも有効なビタミンやミネラル類を含むことがわかり、地上界に住む使い「元使い」
達が勤める企業と提携して、地上界での普及活動を行っていると以前会った時に説明された。
サンプルを3袋もらったので試しに飲んでみたところ、体調が良くなる感じがしたので今は近所のドラッグストアで購入し、毎朝食後に飲んでいる。
龍星は難癖をつけるがのごとく眉をひそめていた。
「知ってるん?」
「天上界のあくどい人間利用方法として専ら不評だ」
「利用って…平等な関係じゃないの?」
「平等と言いながら、結局自分達の都合の良いように利用しているだけだろう。
天上界にも魔界にも人間は邪魔な存在なんだよ本来は。それを全て排除するわけにもいかないから上手く利用しているだけだ」
「嫌ってるなあ天上界」
天上界と魔界の対立に関しては私の知るところではないが、一つの世界で育ってきた環境であれば止むを得ない考え方なのかもしれないと思った。
「はい、どうぞ」
私はほうじ茶が入った湯呑を2つ、ダイニングテーブルの上に置いた。
「ありがとー」
仁達は湯呑を取りふうふうしてから飲んだ。
「ああ、美味しいなあ~ほっとするなあ~星太郎さんもどうぞ」
幸せ顔でお茶を勧める仁達。
彼にも「星太郎」呼びにされた龍星は否定する気力もなくなったのか、無言で湯呑を持ち、おそるおそる口元に近づけ一口飲んだ。恐るべし茶の力。
「…どう?」
「う、美味いと思う」
龍星は初めて口にした物が意外といけることがわかったのか、先程よりも表情が柔らかくなっていた。
「んで、魔力移動のことやけど、うちに移動したなんて信じられへんのやけど」
シンク前で立ったままお茶を飲み干した私はダイニングテーブル前まで移動した。
「魔力を使って試しに何かしてみればいい」
「何かって?」
「さっきのように水を出してみるとか、思い描いた物を念じればだいたいの物は出てくる」
「抽象的な…うーんと、じゃあ水で。出てこい!」
場はシーンと静まり返ったままだ。
「もう1回!」
私は指を反らせ手の平に力を込めたが、それでも何も起こらない。
「ええい!何でもいいからとにかく出てよ!」
やけくそになって叫ぶと、シュワー!と白い糸状の物が手の平から束になって飛び出た。
「うわあっ!なんやこれ」
「細い糸やね」
仁達は冷静に分析し、つんつんと指で突っついた。
「よりによってなんで糸なんやろ」
肩を落としている私に龍星は平然とした様子で
「箏の影響じゃないのか?」
お茶をすすった。
「糸…絃のこと?でもこんな細くないし」
出た糸の本数を数えてみると13本あった。
「おおっ!13本、お箏の絃の本数と同じ…って偶然やろ」
「魔法に偶然はない。強く思っているものが現れたんだろう」
「うちの頭の中は箏だらけか!間違ってはないけど」
「鍛えようによっては価値があるものだ。これで魔力が移動したことがわかっただろう」
「うん…魔法が使えるっていうのは。でも、緩河ストックでもうちと龍月のコードでもない所に移ったってどういうこと?」
「場所は不確かだが、緩河システムに何らかの問題が生じた可能性がある」
「システム?緩河てセキュリティ対策とかあるんや。そこじゃなくても魔界のどこかに保管しておいたら良いんじゃないん?」
「昔は今よりも治安が悪かったため先代魔王が緩河ストックを考案したらしい。 同界に保存しておくよりも遥かに安全性が高く、余程のことがない限り所有者以外には絶対に力が渡ることはない」
「その『余程のこと』が起こったわけなんか」
「ああ…」
お茶を飲みきった彼は何やら思案顔だった。
「魔界ってジメってるだけかと思ってたけど、万全のセキュリティシステムがあるとか意外と技術が進んでるんやな」
私は正直に今までの思い込みと偏見を吐露した。
「魔力が移った理由は不明にしても、安全な場所がうちと龍月のコードってことやけど、そこまでして力を移動させたかった詳しい理由を聞いてない」
「それは、まあ…それほどなくてもいいかと」
これまで問いに対して短くはっきり答えていた彼が口ごもった。
「おすそ分けみたいなものじゃないの?」
仁達がやんわりと尋ねた。
「そんな親切心ないよ、この人には」
私は無下に否定した。
そっぽを向く彼に腑に落ちない私達だったが、私はあることを思い出した。
「あ、ゴミ出しに行かんと!ちょっと行ってくるよ」
パッと立ち上がると、キッチンのゴミ箱前にまとめてあったゴミ袋を手に取った。
「えっと…戻るまでしばしご歓談ください」
気まずそうな雰囲気から一抜けた私はそそくさと部屋を出た。
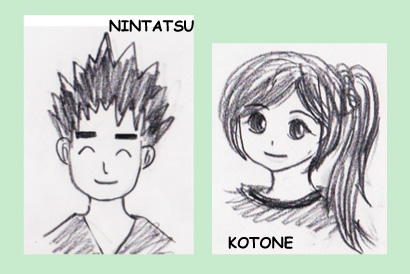
そのわりに今日は朝からやけにじめじめと湿っぽい。 梅雨入りにはまだまだ遠いはずなのに、時折生温い風が頬を撫で、気分まで憂鬱になりそうだった。
私の名前は凛堂琴音(りんどうことね) 年齢は30歳と約半年。
自分の中にもう一つ別の魂が存在することを除けば、ごくごく普通のどこにでもいる平凡なパート主婦である。
別の魂というのは人間ではなく、天上界の神の「使い」と魔界の「魔物」 の間に生まれたハーフである。名を龍月(りゅうげつ)という。
彼女の両親はとある事情により2世界では育てることができず、体が形成される前に魂を地上界、すなわち人間が住むこの世界に落とした。
そして、たまたま私の魂の型と適合したため滞在することになった。
約半年前、生まれて30年目にして初めて龍月と会うことができた。
そのきっかけとなったのが私の誕生日だった。
彼女の婚約者を名乗る日向(ぴゅう)という使いの男性が天上界から訪ねて来たことだった。
「夢逢石(むおうせき)」という石を使えば夢の中で龍月と話ができるというもので、半信半疑の私はこの石を使わせてもらい、何度か彼女と話をすることができた。
けれどもこの石は実は魔力で精製されたもので、継続使用すると使用者の命を奪ってしまう恐れがあったため全て破壊された。
それ以後は龍月と会うことも頭の中で声が聞こえてくるということなどもなかった。
私は2ヶ月ほど前に、住み慣れた京の都から美濃の地に引っ越してきた。
念願のマイホームを建てたのである。
ここは全国でも有数の柿の生産地のため至る場所に柿畑がある。
柿の木は知っているとはいえ、せいぜい他所の家の庭やお寺の境内で見かける程度であった私には、畑一面に低木の柿の木が広がっているというのは新鮮な光景だった。
木には青々とした若葉が繁り、白黄色の小さな花が爽やかに映るが、夜になると枝の別れ具合が長い両腕を広げて獲物を待ち構えている怪物のシルエットに見えてしまい、日が落ちてからはあまり近づきたくない場所だった。
それなのになぜ日没後に外出しているかというと、夕食準備中に牛乳が殆ど残っていないことに気づいたからである。片付けを済ませた後、最寄のスーパーまで買いに行っていたのだった。
ようやく歩き慣れた畑道。雨は既に止んでいる。
私は外灯の近くでふと足を止めた。
静寂の中、かすかに陰鬱な気配を感じた。
(雨のせいかな…)
気に止めず歩き出そうとすると
「おい」
いきなり後ろから声をかけられた。
「えっ?」
びくっとした私が振り返った先には鋭い目をした男性が立っていた。
黒髪に黒っぽい瞳、歳は20代後半くらい。
初夏だというのに黒のモッズ風コートを着ていた。
そのコートというのも少し変わっていて、フロントが短めの斜め比翼仕立てになっており、端が白と深い黄色の色で縁どられ、袖周りもまた同じラインのデザインだった。
身長の割には華奢な体つきで、見目は良いけれどもネガティブな草食系男子といった印象を受けた。
「うん?ええっと…ああっ!」
私は見覚えある姿に魂消げた。
「龍…?ほし…星太郎!」
「龍星(りゅうせい)だ」
彼は眉間に皺を寄せた。 本名はわかっていた。
だがあまりにも唐突すぎたのと、私の中でやたら「星」の印象が強かったためか全然違う名前が口をついて出た。
「あ、うん、そうやった。ってなんでこんなとこにいるん?もしや不意打ちか!?」
私は安さに負けてつい購入してしまった特売の大根をエコバッグから取り出し身構えた。
龍星は生粋の魔物で、龍月の父違いの兄である。
初めて彼に会ったのは5年近く前のこと。
「お前の弾く箏(こと)の音色が原因でオカンが病気になったんだよ!どうしてくれるんだよ!」と要約すればこんな感じで、一方的な敵対心を持たれ命まで狙われるという事件があった。
日本の弦楽器の一つ「箏」、桐でできた本体に13本の絃が張られた楽器だ。
学生時代私は箏曲部に所属しており、卒業後も月に何度か顧問の先生の所へお稽古に通い続けている。
5年前、傷心の日々を送っていた私は箏を心の拠り所にしていた。
けれども、その箏を奏でる音が魔界では不協和音となり騒音被害を出していたらしい。
信じられないかもしれないが、この世界は人間たちが暮らす地上界の他に、天上界と魔界の2つの世界とも繋がっているらしい。
天上界には神様と彼らを手助けする「使い」と呼ばれる者が住み、天上界の者達は、神様の意向を人間に伝える役割と同時に人間を正しい方向へ導く活動を行っている。
一方魔界では、魔王を中心とした「フレリ」という組織で構成されており、彼ら魔物は人間の憎しみ、悲しみ、怒りなど負の感情につけ入り悪の道へ誘おうとしている。
なぜ魔界に被害が及んだかというと、龍月の魂が天上界から地上界へ落とされる際、彼女の父から、地上界でも幸せに暮らせるようにと「絶対的な祈り」を込められたためだった。
その祈りによって私の悲しみの感情と箏の音色が共鳴し合い、魔界では騒音被害が広がってしまうという事態が発生したのだった。
心の支えでもあった箏をやめるわけにもいかず、私は「こてぃすと」の技を習得することに決める。
「こてぃすと」とは箏演奏者であり、かつ箏術(ことじゅつ)を使う者のことを指す。
箏術とは演奏者の気持ちによって、聴く人の心の有り方を変化させる一種の術で、箏を演奏する際に使う爪を持っていれば使用できる。
引っ掻くように払うと風を起こしたり、複数の絃鳴らすと衝撃波を発生させたり、防壁を作れたり等、バラエティに富んだ技を繰り出すことができる。
基本の箏術を習得した私は彼に腹蹴りをくらうという暴力を振るわれたりもしたが、最終的には彼の母が現れ無事であることと、箏の音色は心の持ちようで様変わりし、騒音にならないという事実が判明した。
これでめでたしめでたしと思いきや、魔物およびフレリ達は、地上界で暮らしている使いの魂が入った人間を探し出し、片っぱしから天上界に強制送還または排除するのが目的なので、事情を知らぬ魔物達が私もその使いの一人とみなして襲撃してくるかもしれないということで、引き続きこてぃすととしての活動を余儀なくされた。
このような経緯で彼には良い思い出が全くなかった。
それゆえ久しぶりの再会といえど躊躇と驚き以外の念は沸き起こってこなかった。
そもそも魔物というものは直接人間に関与することはないらしく、このように人前に姿を現すということは禍いをもたらしにきたのではないかと自然と警戒心を抱かざるを得なかった。
そんな私の心を見透かしたのか龍星はため息をついた。
「別件で近辺を通りかかっただけで特に用はない」
「じゃあ声かけんでもええやん」
「……」
呼び止めといて用はないってどないやねん!と呆れたが、彼はまだ含むところがあるような複雑な表情をしていた。
「こてぃすとは辞めたのか?」
その瞬間私はギクリとした。5年前の去り際の自分の台詞を思い起こした。
「こてぃすとの特訓をして魔物なんか追い払ってみんなを守る」とか正義のヒーローばりの意気込みを宣言していた気がする。
若気の至りだったと振り返り近況を伝えた。
「辞めてはないよ。もしもに備えて、技をすぐ出せるようにはしてるけど、近づく魔物もいなくなったし、今は悠々自適な箏ライフを楽しんでるよ」
箏爪(ことづめ)を持参していないというのに私は「すぐに出せる」などと大嘘をついてしまった。
「そっちはどうなん?お母さんは元気?」
会ったついでなので気軽な感じで尋ねた。
「変わりなく過ごしているようだ」
「一緒に暮らしてるんかと思った。龍月もお母さんから話聞いてたって言ってたから」
「近い所にはいる」
「一人暮らしってこと?」
彼は頷いた。思いのほか会話が弾まず、私が質問攻めしているようだった。
「そういえば、一緒にいたお付の女の人は?」
「紗佐(ささ)か?あいつは俺の部下で普段は別の職務についている」
「フレリやったっけ。そんな組織体制やったんや」
すると彼は突然バツが悪そうに視線を逸らした。
「龍月から色々と聞いている。その…あの時は悪かったな、早とちりして」
「え、いや、もう昔のことやし…」
私は狼狽した。あの凶悪と言っても過言ではない龍月の兄が数年ぶりの再会にしてまず謝罪の言葉。
敵意むき出しの当時の彼とは打って変わってしおらしくなったというか、とげとげしさがなくなった気がする。
いや、実は物静かな性格で、執着している事柄に触れると豹変するタイプだったのかもしれない。
「ところで、お前は魔力を持つことに抵抗はないか?」
「魔力?持ったことないから何とも。 家事が捗るなら使いたいもんやけど…何で?」
「自分の魔力の保管先を探している」
「魔力を保管?自分で持ってるのが全てじゃないの?」
「日常使う力とは別に、緩河(ゆるかわ)にいくらか蓄えておけるようになっている」
「ゆるかわ?」
「天上界では星空(ほしぞら)と呼んでいるものだ」
「星空って、確か魂が彷徨ってる空間やったっけ…」
私はまだそう遠くない過去の記憶を手繰り寄せた。
半年前、龍月と会った時に彼女の魂が「星空」といういわば天上界と魔界を行き来できる「みち」に存在することを知った。
「呼び方違うんや。魔物も利用してるん?」
「緩河は何層にも重なってできている空間だ。浮遊魂はその最上面…最上面に見える位置に存在する。対して、魔力保管(ストック)スペースはその下に設けられている。
従来魔物には、基本的に備わっている魔力と保管用の魔力の二種類ある。魔力が強いフレリ達は原則として緩河ストックを利用しなければならない」
「盗まれたりするから?」
「奪取対策も兼ねているが、特定のフレリのみ強大な力を得ないよう調整するためだ」
「ふうん。それなら星空…緩河に保管しとけばええやん。うちフツーの人間やで」
その途端彼の表情がやや曇った。
「フツーの人よりは魔界や天上界と関わってしもた人間かな。でも、生活には何も影響出てないよ」
「そういう奴が適しているんだ。お前達のコードの隙間なら安全だろうと」
「隙間収納にぴったり!みたいな言い方やな」
コードというのは人の魂から出ている線状のようなもので、私と龍月はその型が一致するらしい。 通常2つの魂の間にはわずかに隙間が空いている。
そんな狭い所に自分の魔力を保管したいなんて全く理由がわからない。
「龍月はお前の判断に任せると言っていた」
「ホントに?なんかマズイこと考えてない?」
「いや、そんなことは…」
「嘘や。だいたい天上界や魔界から誰か来る時は厄介事持ち込みって決まってるんや。龍月のお父さんやってそうやったし」
「天上界の奴らと一緒にするな。上手くいけば移動作業は数分で終わるはずだ」
「そのはっきり言い切れてないのが怖いんやけど。他にも魂持ってる人いるやろ」
「お前暇だろう」
「人を暇人にせんといてよ。こう見えて仕事してるんやからな」
私はデリカシーのない彼にイラっとした。
「そういうわけで申し訳ないけど、お役に立つことができません…じゃっ!」
私はくるりと前を向くと数10メートル先の自宅に向かって足早に進み出した。
(全く人の魂をなんやと思って…でも、魔法使ってみたかったかもなあ…って、あかんあかん!魔物の誘惑にのるなんて!)
私は両頬をパチパチたたいて気を引き締めた。
ふと前方に目をやると、自転車にまたがった上下ウコン色の寝間着姿のおじいさんが近づいて来ていた。かなりフラフラ運転だ。
しかもその後ろからは乗用車が距離を縮めていた。
おじいさんは一旦立ち止まり後ろを振り返ると車に気づき、再びハンドルを握り直すと加速した。
が、フラフラ運転は変わらず、むしろさっきよりも蛇行運転がひどくなり、車も追い越しできない状況だった。そんなことおじいさんはつゆ気にも留めていない。
私は道路脇側溝まで寄った。寄りすぎれば雨で湿った草花に足を滑らせ、運が悪ければ顔面から畑へダイブして泥まみれになってしまうのは明確である。
おじいさんが道路脇に寄ったためか、背後にぴったりくっついていた車が少しスピードを上げて追い越そうとした。
またもやおじいさんは車の前にふらーり、そして今度は私の方にゆらーり…
(え?避けやな…!って)
「あっ!」
左足がずるっと滑り、バランスを崩して手をバタバタさせていると、腕をがしっと掴まれた。
「星太郎!ありが…うわっ!落ちる!」
体を支えてくれるかと思いきや、龍星も一緒になって畑に落ちかけたその時、ゴン!と彼の頭に額をぶつけた。
ズキッと痛みが走った。
「いたたたた…」
どたっと尻餅をついた私はどうにか体を起こした。
幸いなことに乾いた土の上だったので泥まみれになることはなかった。
私は砂を軽く払うと向かいに倒れ込んだ龍星に違和感を覚えた。
「あれ?」
起き上がった彼の姿はどう見ても子供だった。
175センチはあったであろう身長が約30センチは縮んでおり、私よりも小さくなっていた。
人間でいうなら小学校5、6年生くらいだろうか。それだけではない。頭には左右に広がった柿の木の枝のような鹿の形に似た角が2本生えていた。
「ツノ?星太郎って鹿の魔物やったん!?」
「違う…だいたい魔界に鹿はいない」
彼は静かに怒っていたが「星太郎」呼びについては特に触れなかった。
大人の姿と比べて、どこかしら幼さが残っている顔つきに少しだけ警戒心が解れた。
「角なんてあったんやな」
「普段は隠している。人間に似せたほうが警戒されづらいからな」
彼はそう言って目を伏せた。
「へえ~てっきり、いろんなとこにぶつけたり引っ掛けたりするからやと思った」
「そのバカな発想はどこから来る?」
「バカな発想じゃないよ、斬新と言って」
呆れている彼に私は胸を張って言い返した。
「こういうのって、もう1回同じ現象起こすと戻ったりするんちゃう?」
「こら、やめろ!」
私は有無言わせず、彼の額めがけて頭突きをかました。
ゴツーン!
「痛い!」
結果、痛かっただけで彼の姿は小さいままだった。
「痛ってぇなバカ…」
「ごめんごめん」
額をさする彼に私は軽く謝った。
「たまに大きな衝撃を受けると縮むことがある。大抵数日すれば治る」
じゃあ、大事には至らないのかとほっと安心しようとしかけた時、彼の表情が強ばった。
「まずい」
私が何がと問いかけようとする前に
「手を出せ」
「手?え、あ、はい」
彼は私の腕をぐいと掴むと手の平を上に向けて思い切り叩いた。
バチーン!
「痛ったい!何する…え、水!?」
それはまるでミニ噴水とでも名付けられるかのように、勢いよく水を噴き上げていた。
「どっから出てきたんこれ?」
あたふたする私に彼は意気消沈した様子で言った。
「どうやらさっきの衝撃で魔力がお前に移ってしまったらしい」
「もしかして謀ったん?」
「お前達のコードには飛んでいない。別の場所だ」
「手放したかったなら結果オーライじゃ…」
「それがストックまるごと飛んだようだ。だから魔界へ帰る力も残っていない」
「帰れへん…?前の時は魔窟(まくつ)とかいうとこから接触してたやん」
魔窟とは魔物が棲む魔の巣窟のことで、自在に空間を作ることができると、以前龍月の父から説明を受けたはずと曖昧な記憶をたどった。
「魔窟は魔界の特別空間であって、直接地上界と接触しているわけじゃない」
「え、じゃあ、今日はどうやってここへ?」
「ワープだ」
「ワープ?そんな魔法のようなことが…ああ、魔物やから魔法使えるか」
私はなんだか頭が痛くなってきた。
「と、とりあえず家へ戻ろう。詳しい話聞くから…」
彼は拒絶することなく静かに頷いた。
自宅に到着して玄関ドアを開けると、パタパタパタと駆けてくるスリッパ音とともに夫の仁達(にんたつ)がにこやかに出迎えてくれた。
「おかえり~…その子は?」
私の後ろにいるフードを目深にかぶった少年に仁達は目をぱちくりさせていた。
「星太郎」
「違う…その変な呼び方やめろ」
龍星は横目で私を睨んだ。
大人に比べて気迫も半減され、怖くなくなっていた私はぷぷっと笑った。
「本名は龍星」
「龍星って、龍月のお兄さんの?どう見ても子供のような…あ、僕は琴音ちゃんの夫で凛堂仁達(りんどうにんたつ)と言います」
初対面でもすぐにその違和感には気づいたらしい。
それにしてもさすが記憶力抜群の仁達。
3年以上も前に話した登場人物をよく思い出せたものだ。
「そうそうその人。偶然そこで会うて、ゴツーンて頭ぶつけたら小っこくなってしもてさー。おまけに魔力もほぼスッカラカンになって…いや、移動やっけ?よくわからんのやけど…」
「ふーん、そうなんか…とにかく、座ってゆっくり話そう」
リビングへ案内しようとする仁達に龍星は躊躇いの表情を見せた。
「上がるのか…?」
「他に選択肢が?」
「…わかった」
「あっ、土足厳禁なんで」
彼は渋々承知すると靴を脱いで玄関に上がり、さっとフードをとった。
仁達はぎょっとしていた。
「わあ、すごいもの付けてるんやね…」
「元から付いてるもんやで」
「…そうなんや。てっきり何かのイベントで仮装でもしてたのかと思ったよ。ははは」
温厚篤実な彼の時たま出る天然さに私も驚きを隠せないことがあった。
龍星は特にコメントせず黙って見つめていたが、玄関正面の階段を見上げると厳しい顔つきになった。
その視線の先には1匹の斑模様の動物が毛を逆立てていた。
つぶらな瞳と丸い耳、ふさふさの長い尻尾が特徴の小さな虎である。彼は箏の精霊ワラビ。
ワラビは私の以前使っていた箏の精霊である。普段は滅多に姿を見せない気難しい性格の彼が、今はグウゥと唸り声を出して龍星を睨みつけていた。
お互い一歩も動かなかったが、数秒経つとワラビは階段を駆け下り、大きく口を開けて龍星に飛びかかった。
龍星は腕で払いのけたが、ワラビはもう一度頭めがけてジャンプしようとした。
「ワラビ!やめっ!」
私は彼らの間に入ったが、頬に軽く猫パンチを食らった。
「痛っ!何をそんなに荒立ててるん?昔のことはいいやろ」
「魔物が地上界に現れることは凶事でしかない」
彼もまた5年前の事件当時、被害にあった1匹である。精霊は、魔物が容易に地上界の人間に近づけないように守る役割も担っている。
ワラビは低い声で答えたが私は首を横に振った。
「今は魔力カラッポやって。何もできへん、人間以下なんやで」
「それは語弊があると思うよ…」
仁達の呟きツッコミに龍星は同調していると思われるような不服そうな眼差しだった。
一触即発ムードの中、階段の手すりの上を滑り落ちてきた小動物がいた。ゼンマイである。
ゼンマイは私の2つ目の箏の精霊で、ネズミとキツネザルを足して二で割ったような体型、身長25センチほどの生き物である。目が異常にくりっとしているため、笑うと特に珍妙な面になる。性格は好奇心旺盛でマイペースだった。
ゼンマイは龍星の膝にぴょんと飛び乗ると、トトトトと上に向かって走っていき、肩までたどり着くと頬をすりすりとこすりつけた。
「何のつもりだ?」
彼はゼンマイをひょいとつまみ上げた。ゼンマイは嬉しそうに目を細め、手足をぶんぶん振っていた。
「ふぬぬぬーん!ふぬぬぬっ!」
「何て言ってるん?」
私はこの中で唯一ゼンマイの言葉が解せるワラビに通訳を求めた。
「よろしく鹿の精霊さん…と」
ワラビは棒読みで訳した。
「鹿…?ぷっ、ナイスボケ!ゼンマイ!」
「ふぬーん!」
私とゼンマイはハイタッチするように指を合わせた。
「あ、ワラビもう行くん?」
ワラビは自室…箏の置いてある2階へ戻ろうとしていた。彼は立ち止まりちらりと振り返ると
「害がなさそうなら用はない」
言い残し階段を上がっていってしまった。
ゼンマイの振る舞いを見て「安全な魔物」だと確信したのだろうか。
ゼンマイといえば、今度は龍星の頭に乗っかって角を指でつついてみたり、ふさふさの尻尾でぽんぽんと跳ねてみたり、遠足の自由行動の園児のように無邪気に遊んでいた。
「鬱陶しい」
彼は手で払いのけると、ゼンマイはポーンと飛ばされた。床に激突するかと思いきや、くるくるくるっと回転し見事に両足で着地した。
「ふぬぬ~ん!」
フットワークの軽さに感動した私と仁達。
「すごい!」
拍手を送った。
「ゼンマイのおかげで助かったよ、ありがとう」
私はしゃがんでゼンマイの頭を撫でた。彼は喜ぶと再び龍星の脚に飛び乗った。
そして今度はお腹あたりに飛びつくと、よじよじとそのまま一直線に上り、肩まで来るとちょこんと座った。
「ふぬーんぬん」
ゼンマイは龍星を見上げて楽しそうに鳴いていた。
「ぷっ…めっちゃ懐かれてる…同類やと思われてるやん。よかったな」
私は爆笑寸前になったのを必死にこらえていた。
冷酷なイメージだった彼が子供の姿になった途端、魔物以前に精霊と間違えられるというなんとも微笑ましい光景に愉快な気分だった。
「邪魔だ」
不愉快そうな龍星はゼンマイを摘み軽く放り投げた。ゼンマイは
「ぬふーん」
と飛び上がりその勢いのまま階段を駆けていった。
一段落後、私達はダイニングに入った。
ダイニングリビングが一体化したLDKスペースは、全体的に明るい温かみのある茶色でまとめられ、アクセントとして引戸や間仕切り、ダイニングテーブル椅子には格子デザインを取り入れた和モダンテイストに仕上げてもらっていた。
のどが渇いていた私はキッチンへ向かった。
お茶を飲もうとシンク横のカウンタースペースに置いていた耐熱ガラスポットのフタを取った。
「星太郎もお茶飲む?」
冷蔵庫を開けて茶葉を選んでいた私は龍星に尋ねると、彼は神妙な顔をした。
「おちゃ?」
「魔界にはないんか。お茶は大多数の日本人が飲んでる飲み物やな。一般的に緑茶のことを指してて、緑茶にも、煎茶、かぶせ茶、玄米茶、ほうじ茶とかいろんな種類があるよ。
種類の大きな違いは葉っぱを日光にあてる時間の違いかな。玉露とかかぶせ茶は日照時間が少ないから、苦味が少なくまろやかな口当たりになる…」
「待て。そんな長い説明は求めていない」
お茶の種類の説明を遮った彼に仁達は
「琴音ちゃんはお茶通なんやよ」
と微笑んだ。
「通まではいかんなあ。色んなの飲んでるうちに覚えただけ。寝る時間前やし、カフェインの少ないほうじ茶でいい?」
「ああ、うん」
龍星は何でもいいやというふうな返事をした。
私が保温ポットの湯を注いでいると
「リリフか」
彼はキッチンカウンター脇に置いてあった白いチャック付き袋を手に取った。
袋には 「リリフ4193~天からの恵み~」という文字の下に、双葉を象ったファンシーなキャラクターのイラストが描かれていた。
「リリフ4193(よいくさ)」は天上界で育てられたリリフという薬草を原料にした爽快味のサプリメントである。龍月の父が仕える神様がリリフを育てており、天上界では主に解毒、浄化剤として使われていた。
それが人間にも有効なビタミンやミネラル類を含むことがわかり、地上界に住む使い「元使い」
達が勤める企業と提携して、地上界での普及活動を行っていると以前会った時に説明された。
サンプルを3袋もらったので試しに飲んでみたところ、体調が良くなる感じがしたので今は近所のドラッグストアで購入し、毎朝食後に飲んでいる。
龍星は難癖をつけるがのごとく眉をひそめていた。
「知ってるん?」
「天上界のあくどい人間利用方法として専ら不評だ」
「利用って…平等な関係じゃないの?」
「平等と言いながら、結局自分達の都合の良いように利用しているだけだろう。
天上界にも魔界にも人間は邪魔な存在なんだよ本来は。それを全て排除するわけにもいかないから上手く利用しているだけだ」
「嫌ってるなあ天上界」
天上界と魔界の対立に関しては私の知るところではないが、一つの世界で育ってきた環境であれば止むを得ない考え方なのかもしれないと思った。
「はい、どうぞ」
私はほうじ茶が入った湯呑を2つ、ダイニングテーブルの上に置いた。
「ありがとー」
仁達は湯呑を取りふうふうしてから飲んだ。
「ああ、美味しいなあ~ほっとするなあ~星太郎さんもどうぞ」
幸せ顔でお茶を勧める仁達。
彼にも「星太郎」呼びにされた龍星は否定する気力もなくなったのか、無言で湯呑を持ち、おそるおそる口元に近づけ一口飲んだ。恐るべし茶の力。
「…どう?」
「う、美味いと思う」
龍星は初めて口にした物が意外といけることがわかったのか、先程よりも表情が柔らかくなっていた。
「んで、魔力移動のことやけど、うちに移動したなんて信じられへんのやけど」
シンク前で立ったままお茶を飲み干した私はダイニングテーブル前まで移動した。
「魔力を使って試しに何かしてみればいい」
「何かって?」
「さっきのように水を出してみるとか、思い描いた物を念じればだいたいの物は出てくる」
「抽象的な…うーんと、じゃあ水で。出てこい!」
場はシーンと静まり返ったままだ。
「もう1回!」
私は指を反らせ手の平に力を込めたが、それでも何も起こらない。
「ええい!何でもいいからとにかく出てよ!」
やけくそになって叫ぶと、シュワー!と白い糸状の物が手の平から束になって飛び出た。
「うわあっ!なんやこれ」
「細い糸やね」
仁達は冷静に分析し、つんつんと指で突っついた。
「よりによってなんで糸なんやろ」
肩を落としている私に龍星は平然とした様子で
「箏の影響じゃないのか?」
お茶をすすった。
「糸…絃のこと?でもこんな細くないし」
出た糸の本数を数えてみると13本あった。
「おおっ!13本、お箏の絃の本数と同じ…って偶然やろ」
「魔法に偶然はない。強く思っているものが現れたんだろう」
「うちの頭の中は箏だらけか!間違ってはないけど」
「鍛えようによっては価値があるものだ。これで魔力が移動したことがわかっただろう」
「うん…魔法が使えるっていうのは。でも、緩河ストックでもうちと龍月のコードでもない所に移ったってどういうこと?」
「場所は不確かだが、緩河システムに何らかの問題が生じた可能性がある」
「システム?緩河てセキュリティ対策とかあるんや。そこじゃなくても魔界のどこかに保管しておいたら良いんじゃないん?」
「昔は今よりも治安が悪かったため先代魔王が緩河ストックを考案したらしい。 同界に保存しておくよりも遥かに安全性が高く、余程のことがない限り所有者以外には絶対に力が渡ることはない」
「その『余程のこと』が起こったわけなんか」
「ああ…」
お茶を飲みきった彼は何やら思案顔だった。
「魔界ってジメってるだけかと思ってたけど、万全のセキュリティシステムがあるとか意外と技術が進んでるんやな」
私は正直に今までの思い込みと偏見を吐露した。
「魔力が移った理由は不明にしても、安全な場所がうちと龍月のコードってことやけど、そこまでして力を移動させたかった詳しい理由を聞いてない」
「それは、まあ…それほどなくてもいいかと」
これまで問いに対して短くはっきり答えていた彼が口ごもった。
「おすそ分けみたいなものじゃないの?」
仁達がやんわりと尋ねた。
「そんな親切心ないよ、この人には」
私は無下に否定した。
そっぽを向く彼に腑に落ちない私達だったが、私はあることを思い出した。
「あ、ゴミ出しに行かんと!ちょっと行ってくるよ」
パッと立ち上がると、キッチンのゴミ箱前にまとめてあったゴミ袋を手に取った。
「えっと…戻るまでしばしご歓談ください」
気まずそうな雰囲気から一抜けた私はそそくさと部屋を出た。